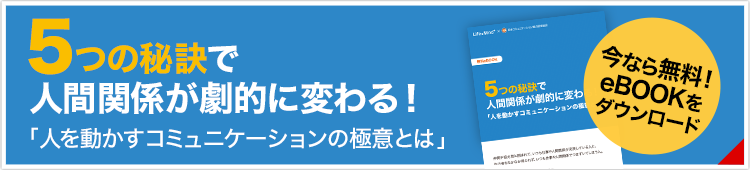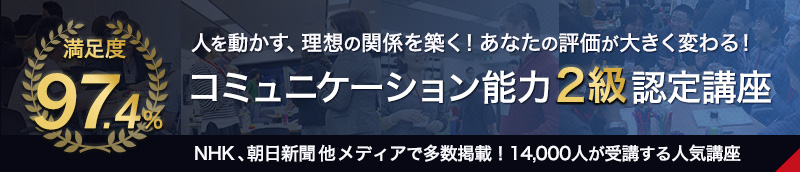つらい職場の人間関係を変える6つの思考法・スキル

心理学者のアルフレッド・アドラーは
「全ての悩みは対人関係にある」というほど、
私たちの人生と、人間関係の悩みは
切っても切り離せないものです。
あなたの職場の人間関係は良好ですか?
「職場での人間関係に疲れて、
じつは転職を考えている。」
こう思っている人も
いらっしゃるかもしれません。
この記事では
人間関係に悩んだときの対処法や、
悩みの捉え方をお伝えしていきます。
完全に割り切る方法から、
人間関係や最終的には
人生を劇的に変えていく方法までありますので
参考になるところを取り入れてみてください。
人間関係での辛い・苦しい状況から
脱するヒントにしていただければ幸いです。
1.人間関係の悩みはどこにでもある

悲しい話ですが人間関係がすべて円満な会社はほとんどありません。
大手人材紹介会社エン・ジャパンの調べによると、離職理由の最も多かった理由に、【社内の人間関係の悪さ】が1位にランクインしています。
- 1位 社内の人間関係が悪かった(28.0%)
- 2位 給与が低かった(12.9%)
- 3位 社風や風土が合わなかった(12.6%)
上記の退職理由に対し、「なぜ、悩みを伝えなかったのか」という問い掛けに、「話しても理解してもらえなかったから」という回答が、3割にも上っています。
このことから、もし、今あなたが転職をしたとしても次の職場でも、大なり小なり人間関係に悩むことは、ほぼ確実にあると思っておいたほうがいいと思います。
では、職場で起こる人間関係の悩みはどんなものがあるでしょうか?
【主な職場の人間関係のトラブル】
- ・上司との折り合いが悪い
- ・周囲と比べると、自分だけ上司から好かれていない気がする
- ・部下が自分の言うことを聞いてくれない
- ・社内で相談できる人がいない
- ・周囲の同僚と壁を感じ孤立している
- ・ハラスメントがある
上記はあくまで一例になりますが、どこの職場でも耳にするトラブルです。
では、なぜこのようなトラブルが世の中のあらゆる職場で起きているのでしょうか?
つぎに人間関係のトラブルに対しての捉え方をお伝えしていきます。
2.劇的に人間関係を変える方法6選

今の職場での人間関係に絶望する前に、人間関係のトラブルに対しての捉え方を最初にお伝えしていきます。
まず、前提として知っていていただきたのは、「人を簡単に変えることはできない」という事です。
ですから、あなた自身の実力や対応能力を上げることが必要になってくる場合もきっとあることと思います。
相手が上司であれば尚更、あなたの言葉一つで変えることはまず不可能でしょう。
また、同僚などから嫌がらせを受ける場合も出てくるかと思います。
「相性が合う、合わない」
「気に入った。気に入らないなど」、
人間関係に悩みはつきもので、これらの状況とどう付き合っていくかによって職場が快適になるのか、苦痛な場所になるのかが変わってきます。
人は人生で約半分の時間を仕事に費やしています。
せっかくのあなたの人生を少しでも快適にしていくためにこの章では、人間関係で苦労されている方へ、
人間関係の辛さのレベルに合わせて状況を変えていく方法を6つご紹介していきます。
2-1.割り切る(スルースキルを身につける)
辛い状況の方のために最初にお伝えしたいのがこのスキルです。
状況によっては、いっそのこと、他人はどうでもいいという考えを持つこと。
この考え方はとても大切です。
もちろん関係上、スルーできない立場の方がいらっしゃることもわかっています。
その場合、心理的には完全に切り捨てて、うわべだけは体裁を保つと考えていただけるといいかと思います。
自分のメンタルを守ることが先決ですからね。
仕事をする上で、職場での人間関係が円滑であることは理想な形ですが、職場は利害関係で集まった集団です。
職場の全員から好かれる必要は全くありませんし、その様な事は不可能だと思います。
職場は仕事をする場所です。
仲良しグループではありませんので、関わり方を変えて、適度な距離を保った関係を築くことも必要です。
ユダヤ人の格言にはこんなものがあります。
10人の人がいるとしたら、そのうちの1人はどんなことがあってもあなたを批判する。
あなたを嫌ってくるし、こちらもその人のことを好きになれない。
そして10人のうちの2人は、互いに全てを受け入れ合える親友になれる。
残りの7人は、どちらでもない人々だ。
(ユダヤ教の教え『嫌われる勇気』より)
あなたが、どのように立ち振る舞っても「全ての人から受け入れられることはない。」
という前提を知っていることで、気持ちが少しラクになりませんか?
ネガティブな人や、あなたに攻撃をしてくる人とは、できる限り距離を置いて、あなたのことを大切に思ってくれる人と関わる様にしましょう。
とはいえ、、
そうも言っていられない場合があるはずです。
そんなあなたのために、続きの章も読み進めてください。
2-2.実力を身につける
時間がかかることですので難しいものではありますが、一番大事なものが「実力をつける」です。
「そんな簡単にできれば苦労しない!」こう思う方もいると思います。
しかし、上司の理不尽な振る舞いや、同僚からの嫌がらせなどをなくす方法として、相手や周囲からの印象を変える。これが最も効果的です。
理不尽な経験をしていると可愛がられている人を見た時に、悔しい思いや嫉妬を感じることも人間ですからあると思います。
有名人が「有名になった途端、周りが高待遇してくれるようになった。
反対に人気がなくなったら、人が急に離れて行った」。
このようなことを言っていることがありますが、残念ながら社会ではそのようなことが起こります。
では、どのようにすればいいのでしょうか。
簡単に言ってしまえば、誰からも文句を言われないほどの結果を出してしまうことです。
あなたの評価も上がり、周囲の人の態度がガラリと変化します。
理不尽を言ってくる上司は何も言わず、むしろ、180°態度を変えてくることもありますし、同僚も以前のような嫌がらせができなくなります。
もちろん、実力を身につけても周囲から嫌われてしまうような立ち居振る舞いをしていると、余計に反発されることも出てきますので、周囲の人と良好な関係を築く努力は必須です。
ここでご紹介している「実力を身につける」というのは、単に仕事の実力だけではありません。
次に、「コミュニケーション力を磨く」方法をお伝えします。
2-3.コミュニケーション力を磨く

あなたの周りには、こんな人はいませんか?
- ・上司から可愛がられる人
- ・協力者が多い人
このような人たちは一般的に、「コミュニケーション能力が高い人」と言われています。
持って生まれたスキルではなく、このように言われる人たちには共通しているコミュニケーションのポイントがあります。
- ・上司と積極的にコミュニケーションを取っている
- ・周囲とも頻繁にコミュニケーションを取っている
- ・普段から周囲といい関係を保つ工夫や努力をしている
「嫌な上司にごますりなんてしたくない。」
「そこまで関わりのない人と、わざわざコミュニケーションを取るのは時間の無駄。」
プライドが邪魔したり、業務の効率重視と考えている場合、こう思う方もいるかもしれません。
しかし、人は接触が多い人に対して、好感を持つ。
という事は心理学的にも明らかになっています。
そして、こうした事ができる人は結局のところ、周囲から評価され、周囲からの協力を得て、自分が仕事をしやすい環境を作っているのです。
コミュニケーション力を磨くことは、仕事でもプライベートでも活かしていくことができるのでとても大切なことなのです。
2-4.理不尽を糧にする
誰しもが良好な人間関係の元で仕事がしたいと思っているはずです。
しかし、そうもいかないのが現実です。
職場で、上司から理不尽な事を言われることもあるでしょう。
自分を蹴落とそうとしてくる同僚も出てくるかもしれません。
あまりにも理不尽な思いをして、精神をすり減らしてしまうのであれば、そこから逃げることも選択肢の1つではありますが、
このような理不尽な経験を糧として、「こんな人になってはいけない。」と反面教師にしてみるのはいかがでしょうか?
今は辛いかもしれませんが、自身の人間性を高める訓練だと割り切ると、悪いお手本が目の前にいることに、むしろ感謝できるようになる日がきっと来るでしょう。
2-5.視点を変える考えを持つ
完全に相手が悪い場合も多いことがわかっている上で、この提案をしたいと思います。
「自分が変わることでうまくいく要素はないか。」
この記事を書いている私自身、人間関係で苦労をしていたとき、上司や人のせいにしていた時期がありました。
確かに誰が聞いても理不尽だと思うこともありましたが、中には自分の捉え方を変えることで接し方が変わり相手もそれに合わせて態度や反応が変わることがあると知りました。
「意固地になっていた」
「自分ももっと柔軟に対応できたはず」
「相手の立場に立てていなかった」 etc
人生で起こる問題のいくつかは、自分を変えることで結果が変わることを知り、それ以来自分を変える部分がないか、相手からみて自分がどう見えているかを考えるようになり抱える問題は激減しました。
相手のせいにし続けても問題が解決しないものもあります。
人のせいにし続けることで自分の成長を妨げていることもあります。
そこで視点を変えて「もしかしたら、自分がもっと上手に対応できていたらうまくいっていたのではないか」という可能性も探るようにしてみましょう。
ひょっとしたら、自分にも変えた方が良かった部分が見つかるかもしれません。
例として2つ挙げていきましょう。
ケース1:
「自分だけが上司から冷たい態度を取られている気がする」という悩みがある場合
あなたに覚えはなくとも、それが、態度だったり表情だったり、ふとした発言に対し、上司に悪い印象を与えてしまい、いつしか上司からの対応が冷たくなっている可能性があります。
自分ではなかなか気づけないものですので、仲のいい周囲の意見を聞いてみることも大切です。
ケース2:
「上司が自分にだけ高圧的な態度を取ってくる」という悩みの場合
あなたの中で不安や、嫌われたくない。
という思いが強すぎて、相手にペコペコし続けた結果、そうした態度が、上司からの高圧的な態度を誘発してしまった。
というケースもあります。
2つのケースで共通することは、「あなた自身は全く身に覚えがない」ということです。
しかし、普段から出てしまっている態度や振る舞い方であなた自身も、人間関係の悩みの種を蒔いていた可能性があるという事です。
このように、人間関係のトラブルには、双方にも要因があることがわかることで、自分の普段のコミュニケーションの取り方や、癖を見直すキカッケになると思います。
2-6.精神的なレベルを1段階上げる
理不尽な思いや嫌がらせなどがあって、辛い状況が続いているかもしれません。 そのようなあなたに持ってみてもらいたい視点がこれです。
これはかなり高度な内容ですが、これができるようになると人生が激変します。
先きほどの章でも書きましたが、自分の立ち居振る舞いや日頃の接し方を変えることで状況が一変することが出てくる場合があります。
人を嫌えば嫌うほど、相手も自分のことを嫌ってくる可能性が上がります。
そうなると、より職場にいるのが辛くなります。
相手と同じレベルで物事を考えていると結果が変わることはありません。
そこで、下記の思考法です。
嫌な人が出てきたからこそ、他の素敵な人のことが際立ち、自分を大切にしてくれる人に感謝の気持ちが出てきたりするものです。
少し遠回りする発想のように感じるかもしれませんが、周囲に感謝の気持ちをもたらすきっかけを作ってくれた、あなたが嫌いな人(苦手な人)に「あえて感謝の気持ちを伝えてみる。」
そうすることで相手の態度が急変することが起こる場合があります。
腹の立つ上司に「いつも厳しく指導していただいているお陰でミスを減らそうと意識できて感謝しています。◯◯課長の視点がとても役に立っています」と伝えたとします。
相手もあなたとの関係が拗れていることはわかっているはずです。
そのあたなから感謝の言葉をもらう。
相手も一瞬、何が起こったのかわからない反応をする場合がありますが感謝をされて嫌な思いをする人はいません。
人間関係の大事なポイントとして、嫌いオーラを出し続けていいことが起こることはまず起こりません。
それよりも、もし可能であれば相手のいい部分を感謝の気持ちなどに乗せて伝えることができると関係が驚くほど良好になることが多々あります。
もしこのようなことが言えるようになると、あなたは1段階上の視点で物事をみていますので、精神的には相手の上から物事を見ていることになります。
このアプローチが確実にうまくいくとは言えませんが、このような視点を持つことで人間関係に大きな影響が出ることに違いありません。
3.自分だけではどうにもならない場合には

前の2章では、悩みの捉え方であなたの行動を変えるヒントをお伝えしてきましたが、少しでも行動に移せそうなものはありましたか?
「あらゆる手を尽くしたけど、今の環境は自分の力ではどうすることもできない。」
という場合についてもお伝えしていきます。
3-1.周囲に相談してみる
あなたは職場内で、悩みを話せる人はいますか?
職場の空気が悪すぎて相談ができる状況ではない人もいるでしょう。
そうした場合には、職場以外の場所で、悩みを話せる人を作りましょう。
あなたの固定観念や先入観、いわゆる「思い込み」ばかりに囚われてしまうと、全てがマイナス思考になり、自分自身を否定する負のスパイラルに陥ってしまいます。
職場の人ではない第三者の意見を取り入れる意味でも誰かに相談することは大切です。
もしかしたら、あなたの思いもしなかった良いアドバイスをもらえる場合もあります。
そして、もし社内で悩みを聞いてくれる人がいるなら、ぜひ、相談に乗ってもらいましょう。
あなたの話を聞いて、相談に乗ってくれた人が、「部長はそんなひどい人じゃないよ。」と同意を得られなかったとしたら、落胆する前に、
先程でもお伝えした「自分にも要因があったかもしれない」と、冷静に考えてみてもいいかもしれません。
もし、カウンセリングを受けたいとお考えでしたら、以下の情報もご参考になるかもしれません。
3-2.退職する
昨今、メディアでも取り上げられているようなパワハラ、モラハラ、セクハラ、こうした事が日常茶飯事で横行している職場では、
あなたの考えをいくら変えても会社の風土して根付いてしまっていてはどうする事もできません。
近ごろ全然眠れない。
突然涙が出てくる。
このような症状は心がすり減ってしまっているサインです。
あなたの身体や心のためにも、早めに職場を変えたほうがいいです。
ただし、一番最初にお伝えした通り職場の人間関係がすべて円満な会社というのは、ほぼ無いという事は前提として認識しておくといいと思います。
こちらの記事では、上記のような症状が出てしまう前にできる対処法について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
最後に

いかがでしたか?
今回、職場での人間関係の悩みについて様々な捉え方と乗り越えるためのヒントをお伝えしてきました。
本記事で提案した「捉え方を変える」という事は、言葉にしてしまうのは簡単です。
しかし、あなたが長い間構築してきてしまった固定概念を塗り替えていくためには、根気よく意識し続けなければいけないかもしれません。
あなたの辛く苦しい現状が、この記事をヒントに少しでも良い方へ向かう事を願っています。
本記事でお伝えした内容の中には、実践的な心理学のスキルを取り入れています。
このスキルを実践することで、少しでも、あなたの悩みや、これからの人生に役立つことができれば幸いです。
日本コミュニケーション能力認定協会では、人間心理に基づくスキルをはじめ、対人コミュニケーションに関するスキルを幅広く扱う講座を行っています。
コミュニケーションの講座では以下の内容を取り扱っていきます。
- ・コミュニケーションの核心を押さえる。信頼関係を築く基本スキル
- ・組織やチームの中で不可欠な、人を動かす力、即戦力としてのコミュニケーション
- ・人間心理を探求し、リーダーシップの要素や対多数の上級コミュニケーションスキル
対人コミュニケーションは、私たちは生きていく上で避けて通ることはできません。
それは仕事であっても、日常生活でも同じことです。
そして、周囲から協力を得て仕事で成果を出している人や、プライベートでも充実した人間関係を築けている人は、共通してコミュニケーションのコツを押さえています。
ご自身を成長させようとお考えの方は、ぜひ学びにお越しください。
あなたの一生の財産となる学びが、この講座の中で見つける事ができれば幸いです。
参考文献:嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え | 岸見 一郎, 古賀 史健
参考サイト
・顧客との共創・協働を大切にして研修を提供するアーティエンス
・おすすめのコミュニケーション研修を紹介 - KeySession
・職場の人間関係が最悪で本気で悩んでる!仕事を辞める前に知っておきたい上司・部下・同僚との関係に振り回されずに働く5つの方法
・仕事に行きたくない朝に泣く人へ!涙を止める対処法と退職時の注意点|CAUPiT
なお、法律などに関する疑問は「身近な法律情報誌リーガレット」で、
わかりやすく情報がまとめられています。
また、IT業界ノートではIT業界の仕事内容や年収情報から、
IT業界へ転職するためのノウハウを発信しています。転職をご検討される際に、ご参照ください。
就活や転職については、以下で発信されている情報もご参考になるかもしれません。
- 新卒の就活情報メディア「キャリアチケット」
- 第二新卒・既卒・フリーターなどの20代向けの就職/転職サイト「第ニの就活」
- 転職でライフスタイルを良くする|転職のサポートドットコム
- 転職サイトおすすめランキングTOP15【特徴や評判・口コミを徹底比較】
- 若手営業職の特化型転職エージェント「hape Agent」
- 20代の【第二新卒・既卒・フリーター】転職・就職支援・就活サイト|キャリモワ
- 25歳の転職はすべき?成功させるために必要なこと|DAINOTE
- オススメ記事|【必読】転職活動する際におさえておきたい心構え
- 外資系・グローバル企業でのキャリアアップを目指すビジネスパーソン向けメディア【外資働くドットコム】
- 客先常駐で一人は辛い?違法?【一人常駐を楽しむコツや対処法】 - CloudInt
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。