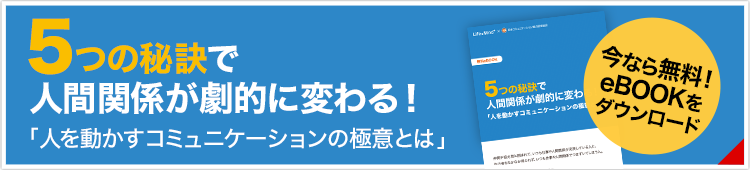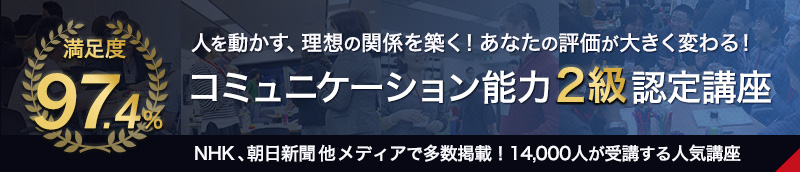自己効力感と自己肯定感の違い|仕事に役立つ自己効力感の高め方3選

「自己肯定感」と似た言葉で、
「自己効力感」というものがあります。
どちらも、
自分に対するイメージという
大まかな認識があるかもしれません。
そこでこの記事では、
それぞれがどのような定義があるかと、
2つの違いについてご紹介していきます。
また、後半では、自己効力感の
高め方もお伝えしますので、
もしご興味がある方は
最後まで読み進めてみてください。
1.自己効力感と自己肯定感の違い
自己効力感と自己肯定感の違いはなんでしょうか。
まずは、それぞれの定義をお伝えします。
自己効力感
自分が起こしたいと考えている行動に対して「できる」と自身で認知していること
自己肯定感
自分の存在そのものに価値があると自身で認知していること
それぞれ、自分に対するイメージについてのことですが、自己効力感は、自分自身が「できる」という実際の行動を起こせる感覚のことで、
自己肯定感は、自分の存在そのものに価値を感じることができている感覚のことです。
自己肯定感は「できる」「できない」や取り組んだ後の結果に関わらず、自分の価値を認めることができている状態です。
自己効力感と自己肯定感はそれぞれが高くなったり低くなったりして、お互いに影響もしています。
自己効力感が高まると、自己肯定感も高まりやすく、自己肯定感が低くなると、自己効力感も低くなりやすいといった傾向があります。
2つとも高い状態を保てるとベストです。
自信を持って、様々なことに挑戦したり、前向きに生きていくことが可能になります。
この記事の後半では、自己効力感を高める方法も具体的にお伝えしていきたいと思います。
自己肯定感とは何か、詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
→ 自己肯定感とは?高い人の特徴5選とすぐに実践できる高め方3選
2.自己効力感を高めるメリット
自己効力感を高めるメリットはさまざまありますが、本記事では大きく分けて3つご紹介します。
2-1.チャレンジ精神を高めることができる

自己効力感は「自分ならできる」という感覚を持つことができるため、これを高めることによって、向上心も強まりやすく、新しいことへのチャレンジ精神を高めることもできます。
逆に、自己効力感が低くなってしまうと、「自分なんかにはできない」と思いやすくなってしまい、挑戦や成長の機会を逃してしまうことに繋がります。
例えば、会社で新しい仕事のチャンスを与えてもらえたとしても、断ったり、他の方に譲ってしまったりします。
チャレンジすることと、その結果は別のものとして考え、新しいことにチャレンジしていくことで、仕事でもプライベートでも、さまざまな経験値を積み、判断力なども高まり、望む結果を手に入れやすくなります。
2-2.落ち込みにくくなる
自己効力感が高くなると、もし失敗したとしても、自分にはできるという感覚を持っているため、「次こそはできる」と気持ちを切り替えることができます。
そのため、失敗やトラブルがあっても、落ち込みにくくなるのです。
筆者も、自己効力感が低くなってしまっていた時期は、仕事で、そこまで大きくない失敗だったとしても、
「一人前の仕事ができない」と感じてしまい、失敗したものとは全く関係ない仕事に対しても、「私なんかでは、うまくできない」と、どんどん落ち込んでしまいました。
そこで、自己効力感を高める方法を学び、行動することによって、失敗しても「次こそ上手くやれる」と思うことができるようになりました。
そして、改善のために何をすべきなのかを、すぐに考えるようになり、新しい仕事に対しても、手を挙げられるようになっていきました。
このように、自己効力感を高めておくことによって、落ち込みにくくなり、何が起きてもブレない、強い軸を持った自分になることができるでしょう。
2-3.やる気を維持することができる
自己効力感を高めることができると、やる気を維持することができます。
なぜなら、「自分にはできる」という感覚が常に備わっているため、結果や状況に左右されずに、取り組んだり挑戦することができるからです。
自己効力感が高いと、自然とやる気のある状態を保つことができます。
逆にもし、自己効力感の高さに波があったとすると、どのようなことが起きるでしょうか。
例えば、新しいプロジェクトを始めたとき、最初は、スタートしたばかりなので、きっとやる気に満ち溢れています。
ですが、途中で解決しないといけない課題に何度も直面し、解決に時間がかかってしまうことがあるかもしれません。
そうした状況が続いてしまうと、「自分には出来ないかもしれない」と考えるようになり、その結果、自信をなくし、やる気も継続できなくなってしまうのです。
やる気を維持するために、気持ちをコントロールしようとしてもそれはなかなか難しいことなので、
自己効力感を高めて「自分ならできる」という感覚を当たり前に感じられるようにしておくことがお勧めです。
3.自己効力感を高める方法3選

2章で、自己効力感を高めることによるメリットをお伝えしてきました。
3章では、自己効力感を高める方法を具体的にご紹介していきます。
3-1.「成功体験」を重ねる
自己効力感を得るためには、「自分にはできるんだ」という感覚を、自分自身でしっかり実感する必要があります。
そのため、小さなことでもいいので、「成功体験」を重ねていくことが大切です。
いきなり大きな目標を掲げてしまうと、達成までに時間がかかって、途中で挫折してしまう可能性もありますし、達成できずに終わってしまう場合もあります。
まずは、小さな目標を立ててみて、それを成功させることから始めてみるのがおすすめです。
筆者は普段、読書をする習慣がほとんどありませんでした。
しかし、「通勤時に読書して本を1冊読み切る」という目標を掲げて、「毎日本を持ち歩き、少しずつ読み進めて、1冊を読み切ることができた」という小さな成功体験を積めたことで、自己効力感が高まる一つのきっかけになりました。
少しずつ自分の中で難易度を上げてながら、「成功する」ことに慣れていくと、自己効力感も高まりやすくなるでしょう。
3-2.過去の成功体験をまとめる
もし、「自分には成功できない」と思ってしまっている場合は、過去に、どんな成功体験をしてきたかを思い出して、まとめてみることもお勧めです。
若手の頃に担当した仕事の経験でもいいですし、もう少し遡って、学生時代の部活や習い事、学校のテストなどでも構いません。
小さなことでも、成功できたことをまとめてみることで、「自分も過去にこんなに成功してきていた人間なのだ」と気づくことができるでしょう。
そうすることで、「これからも成功できる」という感覚を持ちやすくなると思います。
この感覚に慣れていくことを目指していきましょう。
3-3.自分にかける言葉をポジティブにする
自己効力感が低い状況だと、
自分にかける言葉は、
- ・自分にはできない
- ・自分なんかにはもったいない
- ・私には無理だ
などと、ネガティブな言葉を使ってしまうことが多くなりやすいです。
一説によると、人は、1日に2〜3万回ほど自分と対話しているそうです。
もし、周りの人から「あなたには無理だ」という言葉を1日にたった1回聞いただけでも、苦しくなってしまったり、自分はだめだ、、、と落ち込みやすくなるものです。
それにも関わらず、2~3万回、自分にかける言葉がネガティブだとすると、心の内側では、大きなマイナスの影響を及ぼしてしまっている可能性が高いです。
自分にかけている言葉は、自覚しづらいかもしれません。
気付かぬうちに、自分で自分の自己効力感を下げてしまわないように、自分にかける言葉を、できるだけポジティブにすることをお勧めします。
筆者は、もともと自分に対してどんな言葉を使っているのか把握できていませんでした。
そのため、気が向いた時に日記のようなものを書いて、自己評価を文字で見えるようにしてみました。
その内容には、
「自分が◯◯できていなかったからだめだ」
「私なんかが◯◯したら周りから変な目でみられるかも」
と、ネガティブな内容が多くあったことが分かりました。。
これではいけないと感じて、それからは、ネガティブな言葉を自分にかけていると気づけたら、
「あ、いけないいけない。代わりにこう思おう。」と自分との対話を客観的に見て、そして自分にかける言葉を意図的に変えていきました。
急に変えることはなかなか難しいものではありますが、まずは自分が自分にどんな言葉をかけているのかを確認してみることから始めてみましょう。
他にも、自己効力感の高め方をもっと知りたい方は以下の記事もご覧ください。
→ 自己効力感を高める7つの方法!測る尺度や3つのメリットも解説
番外編.健康な心身状態を保つ

自己効力感を高めるためには、健康な心身状態を保つことも大切ですから、番外編としてご紹介します。
健康な心身でいるということは、当たり前に思うかもしれませんが、意外と、ないがしろにしてしまいがちな内容です。
心と体は繋がっていますので、心が健康でないと体も不健康に、体が健康でないと、心も不健康になりやすくなってしまいます。
筆者も、学生時代と比べ、社会人になってから健康を大切にするようになりましたが、これだけでも自己効力感がかなり高まったと感じております。
大学生時代は、毎月風邪を引きがちで、メンタルも安定せず、自己効力感の高さを感じることもほぼなかったのですが、
心身共に健康であるだけで、何かを成し遂げたいと感じた時に100%の自分で、全力で向かうことができるようになりました。
4.最後に
いかがでしたでしょうか。
自己効力感と自己肯定感の違いや自己効力感を高めるメリット、そして高め方をご紹介しました。
もし、自分の自己効力感をより高めたいとお考えであれば、実は周りにいる人の自己効力感を高めることも大切です。
人の自己効力感を高めることは、その人の自己重要感を満たすことにも繋がります。
そして、人の自己重要感を満たせる人は、周りから信頼されたり、好かれやすくなり、周囲に対して良い影響力を持てるようになります。
そうすると、回り回って自分自身の自己効力感も高まりやすくなるのです。
自分や相手の自己効力感の高める具体的な方法を当メディアサイトを運営している日本コミュニケーション能力認定協会では、講座を通してご紹介しています。
心理学を活用して、コミュニケーション能力を飛躍的に高める内容で、経営層の方やビジネスパーソンを始め、営業、事務、専門職や学生の方など、14,000名を超える方々が学びにお越しになります。
ご興味がありましたら、まずは下記から詳細をご確認ください。
無料でダウンロード!
→【無料eBOOK】5つの秘訣で人間関係が劇的に変わる!
「人を動かすコミュニケーションの極意とは」
コミュニケーションの講座を詳しく知る
→「実践的なコミュニケーション能力・スキル」を高める4つの講座
なお、「【資格一覧12種類】メンタルコーチング/メンタルトレーナーのおすすめ!どれがいい?」ではメンタルコーチング・トレーナーの資格が紹介されています。もしも、メンタルコーチングやトレーナーの資格についてはご興味がございましたら、ご覧ください。
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。